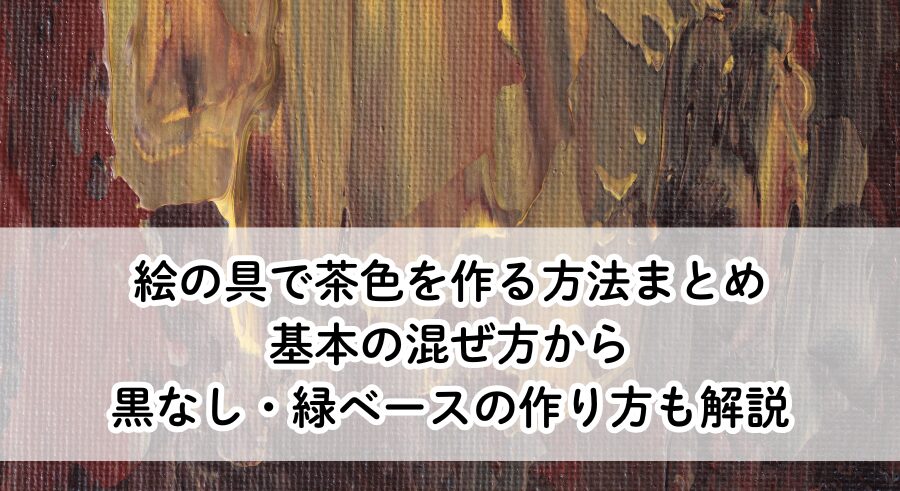茶色の作り方|絵の具で簡単に茶色を作る方法まとめ
絵を描いたり、DIYで着色したりする際に、「茶色」を使いたい場面は意外と多いものです。
しかし、絵の具のセットにちょうど良い茶色が入っていなかったり、イメージ通りの色合いが見つからなかったりして困った経験はありませんか?
茶色の作り方は、一見すると少し難しい印象があるかもしれません。
ただ、実は色を混ぜる際の基本的な考え方さえ理解すれば、誰でも簡単に様々な茶色を作り出すことが可能です。
この記事では、絵の具で茶色を作るための基本的な方法から、黒を使わずに作るテクニック、さらには緑をベースにした応用的な色の作り方まで、幅広くご紹介します。
色の三原色である赤・黄・青を基本に、白や黒、補色となるオレンジ色などを少しずつ加えていくだけで、表現の幅は大きく広がります。
この記事を読めば、あなたも茶色マスターになれるかもしれません。
茶色の作り方の基本

色を混ぜる際の基本的な考え方
色を作る上で最も重要になるのが「色の三原色」という考え方です。
これは、赤・黄色・青の3つの色のことで、これらの原色を混ぜ合わせることで、理論上はほとんどすべての色を作り出せるとされています。
そして、この三原色をすべて同じ割合で混ぜ合わせると、黒に近い暗い色になります。
茶色の作り方の基本は、この三原色のバランスを意図的に少し崩すことにあります。
つまり、特定の色を少し多く、または少なく混ぜることで、暖色系の赤茶色や、落ち着いた黄土色など、多様な茶色を生み出すことが可能になるのです。
色を混ぜるという行為は、単に色を足し算するだけではなく、それぞれの色が持つ特性を理解し、その割合を調整していく作業と言えるでしょう。
この基本的な考え方を頭に入れておくだけで、茶色を作るのがぐっと簡単になります。
必要な絵の具の種類とその特徴
茶色を作るために、まず揃えておきたい基本的な絵の具があります。
それは、色の三原色である「赤」「黄色」「青」の3色です。
これに加えて、色の明るさを調整するための「白」と、色を濃く、深くするために使う「黒」があれば、作れる色のバリエーションが格段に広がります。
赤色は暖かみや血色感を、黄色は明るさや活発な印象を、そして青色は冷たさや落ち着きを色に加える特徴を持っています。
これらの原色が、茶色の微妙な色合いを決める重要な要素となります。
また、使う絵の具の種類によっても、仕上がりは異なります。
例えば、透明水彩絵具は下の色が透けるため、重ね塗りで深みを出すのに向いていますし、アクリル絵具やポスターカラーのような不透明な絵具は、くっきりとした発色で、しっかりと色を混ぜることが可能です。
レジンなどで使用する着色剤の場合も、この基本的な色の組み合わせは同じように応用できます。
基本の混ぜ方と色合いの調整
最も基本的な茶色の作り方は、前述の通り、色の三原色である赤・黄色・青を混ぜ合わせる方法です。
まずはパレットの上で、この3色を同じ量だけ出して混ぜてみてください。
すると、中間の標準的な茶色ができます。
ここからが色合いの調整の本番です。
例えば、出来上がった茶色にさらに黄色を多く加えると、明るい印象の「黄土色」に近くなります。
逆に赤の割合を多くすれば、レンガ色のような温かみのある「赤茶色」を作ることが可能です。
調整を行う際の重要なコツは、色を一度にたくさん加えるのではなく、少しずつ混ぜていくことです。
特に色の影響が強い赤や青は、慎重に量を加える必要があります。
この少しずつの調整作業を繰り返すことで、自分のイメージにぴったり合った茶色を見つけることができるでしょう。
絵の具を使った茶色の作り方

赤・黄色・青を使った茶色の作り方
ここでは、改めて色の三原色である赤・黄色・青だけを使った茶色の作り方について解説します。
この3色だけで作る方法は、最もオーソドックスで、色作りの基本を学ぶのに最適なものです。
まず、パレットに赤色、黄色、青色の絵の具をそれぞれ同じ量出します。
それを筆やペインティングナイフで均一になるまでよく混ぜ合わせます。
たったこれだけで、基本的な茶色を作ることが可能です。
この方法で作る茶色は、黒を混ぜない分、比較的明るく自然な色合いになる傾向があります。
もし、もう少し赤みが欲しい場合は赤を、黄色っぽくしたい場合は黄色を、というように、加えたい色の印象を考えながら少しずつ絵の具を足していくことで、微妙な色調の変化を楽しめます。
3色の割合を変えるだけで、実に多様な茶色を生み出せるため、ぜひ試してみてください。
黒を使った濃い茶色の作り方
チョコレート色やこげ茶色のような、深みのある濃い茶色を作りたい場合には、黒の絵の具を使うと非常に効果的です。
作り方はとても簡単です。
まず、赤・黄色・青を混ぜて基本的な茶色を作ります。
その基本の茶色に対して、黒の絵の具をほんの少しだけ加えるのです。
ここで最も重要な注意点は、黒は非常に強い色であるため、絶対に一度に多く混ぜないことです。
楊枝の先で少しすくうくらいの量から試し、少しずつ、慎重に加えていくようにしましょう。
黒を多く加えすぎると、せっかく作った茶色の彩度が大きく下がり、ただの黒っぽい、くすんだ色になってしまいます。
濃いけれどもしっかりと茶色としての色味を保つためには、黒の量を微調整する丁寧さが必要不可欠です。
薄い茶色を作るための混ぜ方
ベージュやミルクティーのような淡い、薄い茶色を作りたい時には、白色の絵の具が活躍します。
こちらも作り方はシンプルです。
三原色(赤・黄・青)を混ぜて作った基本的な茶色に、白色の絵の具を混ぜていくだけです。
白を加える量が多くなるほど、茶色はどんどん明るく、まろやかな色合いに変化していきます。
理想の明るさになるまで、白を少しずつ加えながら色の変化を確認するのが良いでしょう。
この方法は、肌色に近い色を作る際にも応用が可能です。
また、もう一つの方法として、そもそも茶色を作る段階で黄色を多く配合し、明るめの茶色(黄土色に近い色)を作っておき、そこに白を加えていくと、より自然で綺麗なベージュ系の色を作りやすくなります。
明るい色を作る場合も、色の調整は少しずつ行うのが失敗しないコツです。
緑ベースで茶色を作る方法

緑系の絵の具を使用した茶色の調整
茶色を作る方法は、三原色を混ぜるだけではありません。
実は、「緑」と「赤」を混ぜ合わせることでも茶色を作ることが可能です。
これは「補色」の関係を利用した方法です。
補色とは、色相環で正反対に位置する色の組み合わせのことで、混ぜ合わせるとお互いの色味を打ち消し合い、彩度の低い色、つまり灰色や黒、茶色に近い色になる性質があります。
緑と赤もこの補色の関係にあたります。
市販の緑色の絵の具に赤色を少しずつ加えていくと、だんだんと緑の色味が抑えられ、落ち着いた茶色へと変化していきます。
この方法で作る茶色は、少し緑がかった、カーキやオリーブのような独特のくすみ感を持つことが特徴です。
自然の中にある土や木の幹のような、複雑な色合いを表現したい場合に非常に便利なテクニックと言えるでしょう。
オレンジ色との組み合わせによる茶色のバリエーション
緑と赤の組み合わせと同様に、補色の関係を利用して茶色を作るもう一つのパターンが、「オレンジ色」と「青」の組み合わせです。
オレンジ色は、赤と黄色を混ぜることで簡単に作ることができます。
まずパレットで鮮やかなオレンジ色を作り、そこに青色の絵の具を少量ずつ加えて混ぜていきます。
すると、オレンジ色の鮮やかさが徐々に落ち着き、深みのある茶色へと変わっていきます。
この方法の特徴は、赤みがかった暖かい印象の茶色が作りやすい点です。
例えば、レンガ色やテラコッタのような、暖色系の茶色を表現したい時に非常に適しています。
青の加える量によって、明るいキャメル色から、ビターチョコレートのような濃い茶色まで、幅広いバリエーションの茶色を作ることが可能になります。
具体的な色の割合と作り方の解説
ここまで様々な茶色の作り方をご紹介してきましたが、より具体的なイメージが湧くように、代表的な茶色の割合の目安をまとめてみましょう。
もちろん、使用する絵具のメーカーや種類によって発色は異なるため、これはあくまで一例として参考にしてください。
| 作りたい茶色 | 色の割合の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 黄土色 | 黄色(多) + 赤(少) + 青(ごく少量) | 黄色をベースに、赤と青で彩度と明度を調整するイメージです。 |
| 赤茶色(レンガ色) | 赤(多) + 黄色(少) + 青(ごく少量) | 赤を主体にし、黄色で明るさを、青で深みを加えます。オレンジに青を混ぜる方法も良いでしょう。 |
| こげ茶(チョコレート色) | 赤 + 黄 + 青 + 黒(少量) | 基本の茶色に、黒を慎重に加えて濃くしていきます。 |
| カーキ | 緑 + 赤(少量) | 緑をベースに、赤を加えて緑の色味を抑えていくと、くすんだ茶色が作れます。 |
実際には、これらの割合を参考にしつつ、パレットの上で少しずつ色を試し、自分の目で確かめながら調整を重ねていくことが、理想の色にたどり着くための最も重要なプロセスです。
茶色を作る際の注意点

混ぜる際の色の性質について
絵の具で色を混ぜる際には、それぞれの絵の具が持つ「性質」を理解しておくことが重要です。
絵の具には、下の色を隠蔽する力が強い「不透明色」と、下の色が透けて見える「透明色」があります。
例えば、不透明な絵の具同士を混ぜる場合は、パレットの上で見た色と近い色で塗ることが可能です。
一方で、透明水彩絵具のような透明色を使う場合は、紙の上で色が重なり合って見えるため、パレットでの混色とはまた違った効果が生まれます。
また、絵の具の種類によっては、乾くと色が変化するものもあります。
特にアクリル絵の具は、濡れている時よりも乾いた後の方が少し暗く、濃い色になる傾向が強いです。
このような絵の具の性質を知らずに色を作ると、完成した時のイメージが大きく異なる場合があるため、自分が使う画材の特性を事前に把握しておくことが大切です。
色合いの効果とその調整方法
茶色と一言で言っても、その色合いによって与える印象は大きく異なります。
赤みが強い茶色は暖かさやエネルギーを、黄色がかった茶色は明るさや親しみやすさを感じさせます。
一方で、黒や青が多く含まれる暗い茶色は、重厚感や高級感、落ち着いた雰囲気を演出する効果があります。
自分が描きたいものや作りたい作品のイメージに合わせて、どのような茶色が最もふさわしいかを考えることが重要です。
色合いの調整は、主に「明度(色の明るさ)」と「彩度(色の鮮やかさ)」の2つの軸で考えます。
明度を明るくしたい場合は白を、暗くしたい場合は黒を加えます。
彩度を下げ、色をくすませたい場合は、補色(赤には緑、青にはオレンジなど)や黒、灰色を少量加えることで調整が可能です。
これらの調整方法を使い分けることで、表現したい雰囲気にぴったりの色合いを作り出すことができます。
茶色の種類とその使いどころ
絵の具のチューブには、バーントシェンナ、ローアンバー、セピアなど、あらかじめ作られた様々な種類の茶色が販売されています。
これらは、特定の顔料から作られており、それぞれに独特の色味と特徴があります。
自分で色を混ぜて作る茶色と、これらの市販の茶色を上手に使い分けることで、表現の幅はさらに広がります。
例えば、風景画で木の幹や土を描く際、一種類の茶色だけで塗るのではなく、自分で作った少し赤みがかった茶色や、市販の緑がかった茶色など、多様な色を使い分けることで、より自然で深みのある表現が可能になります。
また、ハンドメイドのレジン作品や粘土細工などで食べ物を作る際にも、チョコレート色やクッキー生地の色など、微妙な茶色の違いがリアリティを大きく左右します。
様々な茶色を知り、その使いどころを考えるのも、創作活動の楽しみの一つと言えるでしょう。
まとめ
今回は、絵の具を使った様々な茶色の作り方について、基本的な考え方から具体的な混ぜ方、調整のコツまで詳しく解説しました。
茶色作りの基本は、色の三原色である「赤・黄色・青」を混ぜ合わせることです。
この3色の割合を変えるだけで、黄土色や赤茶色など、幅広い色合いを生み出すことができました。
さらに、濃い茶色を作りたい時には「黒」を、薄いベージュのような色を作りたい時には「白」を加えることで、明るさの調整が簡単にできます。
また、補色の関係を利用した「緑と赤」や「オレンジと青」の組み合わせは、より複雑で深みのある茶色を作る際の便利なテクニックです。
最も重要なのは、どの方法を使うにしても、色を一度に多く加えず、少しずつ混ぜながら色の変化を確かめることです。
この記事でご紹介した方法を参考に、ぜひあなただけのオリジナルな茶色作りを楽しんで、作品制作に活かしてみてください。