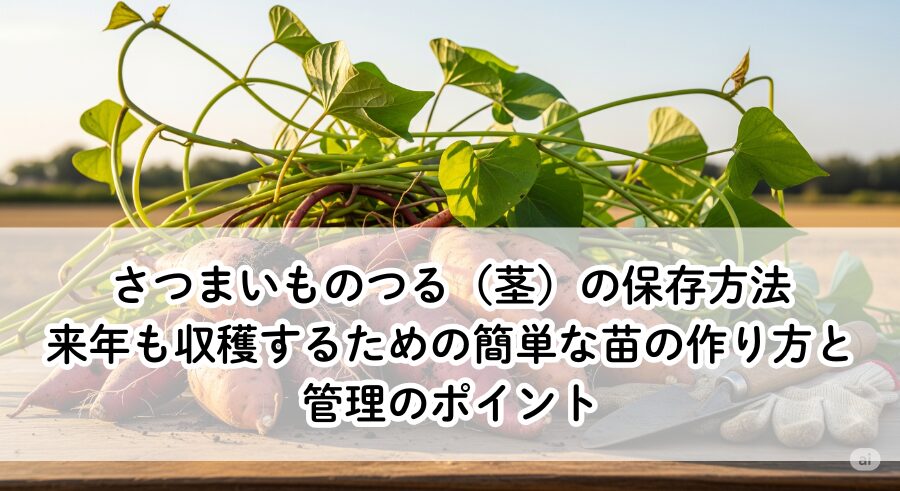さつまいものつる(茎)の保存方法|来年も収穫するための簡単な苗の作り方と管理のポイント
家庭菜園でさつまいもを育てて、たくさん収穫できた時の喜びは格別ですよね。
ところで、収穫の時に大量に出る「つる(茎)」、皆さんはどうしていますか?
多くの場合、そのまま捨ててしまうことが多いかもしれません。
しかし、そのつるを上手に保存しておくことで、実は来年の苗として活用することができるのです。
これには、来年も同じ美味しいさつまいもを収穫できたり、苗を購入する手間やコストを省けたりと、嬉しいメリットがたくさんあります。
この記事では、初めての方でも安心して挑戦できるよう、さつまいものつるの保存方法から、そのつるを使って来年の苗を作る具体的な手順、そして管理のポイントまでを分かりやすく解説していきます。
今年の収穫で出たつるを、来年の楽しみに繋げてみませんか。
今回ご紹介する方法を参考に、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
さつまいもの「つる」を保存する理由とメリット

来年も同じ美味しいさつまいもを収穫するため
さつまいものつるを保存する最大のメリットは、今年収穫したお気に入りのさつまいもを、来年も同じように味わえる可能性が高いことです。
なぜなら、つるから苗を育てて栽培する方法は、親となる株の遺伝的な特徴をそのまま引き継ぐからです。
例えば、今年作ったさつまいもが驚くほど甘くて美味しかった場合、その株から伸びたつるを選んで保存し、来年の苗にすれば、再び同じ品質の美味しいさつまいもを収穫できるというわけです。
お店で苗を購入する場合、同じ品種名であっても、育った環境や個体差によって微妙に味が異なることがあります。
しかし、自分で育てて味を確認した株のつるを使えば、そういった失敗を減らすことができます。
自分の畑で育った、とっておきのさつまいもの味を次の年も楽しむために、つるの保存はとても有効な方法と言えるでしょう。
苗を購入する手間とコストを省く方法
つるを保存しておくことは、経済的な面でも大きなメリットがあります。
毎年春になると、園芸店やホームセンターではさつまいもの苗が販売されますが、当然ながら購入するにはコストがかかります。
家庭菜園で数本だけ育てるのであれば、それほど大きな負担にはならないかもしれません。
しかし、ある程度の数を植えたいと考えている場合、苗の購入費用は意外と高くなってしまうものです。
収穫後のつるを保存して自分で苗を育てれば、この苗代をまるごと節約することができます。
また、春の植え付けシーズンは、人気の品種の苗が売り切れてしまうことも少なくありません。
自分で苗を準備しておけば、春になってから慌てて苗を探し回る手間も省けます。
このように、つるの保存は来年の栽培に向けた賢い準備であり、手間とコストを削減する非常に合理的な方法なのです。
【収穫後が重要】来年のための、さつまいものつる(茎)保存方法

保存に適したつる(茎)の選び方【重要ポイント】
来年の元気な苗を作るためには、どのつるを保存するかが非常に重要になってきます。
まず、収穫した株の中から、最も生育が良かったものを選びましょう。
そして、その株から出ているつるの中から、できるだけ太くてしっかりしたものを選んでください。
病気や虫の被害がない、青々とした健康的なつるを選ぶことがポイントです。
葉っぱが黄色く枯れていたり、茎に黒い斑点があったりする部分は避けましょう。
そういった部分は、冬の間に枯れてしまう可能性が高いですし、病気を来年に持ち越してしまう原因にもなりかねません。
理想的なのは、鉛筆くらいの太さがあり、節と節の間が詰まっている部分です。
収穫の際に、元気そうなつるをいくつか候補として残しておき、その中から最も状態の良いものを選ぶと失敗が少なくなります。
この最初の選び方が、来年の栽培の成功を左右すると言っても過言ではありません。
初心者でも簡単!選べる2つの保存方法
保存に適したつるを選んだら、次はいよいよ冬越しさせるための作業に入ります。
初心者の方でも簡単に挑戦できる代表的な方法が2つあります。
一つは「水挿し」で保存する方法です。
これは、コップや空き瓶などの容器に水を入れ、つるの切り口を浸しておくという非常にシンプルなやり方です。
もう一つは「土に挿す」方法です。
こちらは、プランターや植木鉢に園芸用の土を入れ、そこにつるを挿して管理する方法になります。
どちらの方法にもメリットがありますが、ご自身の管理しやすい方を選ぶと良いでしょう。
例えば、水挿しは土の準備が不要で手軽に始められ、根が出る様子が観察しやすいのが特徴です。
一方で、土に挿す方法は、より畑に近い環境で管理できるという利点があります。
どちらの方法を選ぶにせよ、次の管理方法と注意点を守ることが大切です。
| 水挿しでの保存 | 土に挿して保存 | |
|---|---|---|
| メリット | ・手軽に始められる ・根の観察がしやすい ・土の準備が不要 | ・畑に近い環境で管理できる ・比較的乾燥に強い |
| デメリット | ・水が腐りやすい ・こまめな水替えが必要 | ・土やプランターの準備が必要 ・水のやりすぎに注意 |
冬越し中の管理方法と注意点
つるを無事に冬越しさせるためには、いくつかの重要な管理ポイントがあります。
さつまいもは元々暖かい地域の野菜なので、寒さが非常に苦手です。
そのため、保存場所は凍結の心配がない室内が基本となります。
理想としては、10度以上の気温を保てる、日当たりの良い窓際などが良いでしょう。
水挿しで管理している場合は、水が腐らないように数日に1回は必ず新しい水に交換してください。
これを怠ると、切り口が傷んで枯れてしまう原因になります。
土に挿している場合は、水のやりすぎに注意が必要です。
土の表面が乾いたのを確認してから、たっぷりと与えるくらいで大丈夫です。
冬の間は生長が止まるので、過湿は根腐れを招きます。
冬の間に葉っぱが枯れて落ちてしまうことがありますが、茎の部分が青々としていれば生きている証拠です。
慌てて捨ててしまわないように注意しましょう。
保存したつる(茎)から来年の苗を作る方法

苗を作り始める時期と準備するもの
寒い冬を乗り越えたつるから、いよいよ来年の植え付けに向けた苗作りを開始します。
この作業を始めるのに適した時期は、本格的に暖かくなってくる春先、おおよそ4月頃が目安です。
畑に植え付ける日から逆算して、1ヶ月くらい前から準備を始めるとちょうど良いでしょう。
あまり早くから作業を始めてしまうと、苗が育ちすぎてしまったり、管理が大変になったりすることがあります。
準備するものは、まず冬越しさせたさつまいものつる(茎)です。
それから、つるを切るための清潔なハサミ、そして発根させるための容器が必要です。
水挿しで発根させる場合はコップや瓶などを、土で育てる場合は育苗ポットと新しい園芸用の土を用意しておきましょう。
この段階で古い土を使い回すと、病気の原因になる可能性があるので、できるだけ新しい土を使うことをお勧めします。
簡単3ステップ!水挿しでの発根方法
保存しておいたつるから根を出させる方法はいくつかありますが、中でも最も簡単で失敗が少ないのが水挿しです。
土を使わないので手も汚れず、初めての方でも気軽に挑戦できます。
手順はとてもシンプルです。
まず、冬越ししたつるを、葉っぱが2〜3枚付くように、長さ20cmくらいのところでカットします。
この時、茎にある節の部分がいくつか含まれるように切るのがポイントです。
次に、カットしたつるを、節が2つ以上水に浸かるようにして、水を入れたコップや瓶に挿します。
あとは、日当たりの良い室内の窓際などに置き、毎日水を替えながら管理するだけです。
順調にいけば、1週間から2週間ほどで、水に浸かっている節の部分から白い根が出てくるのが確認できるはずです。
この根が出てくる様子を観察できるのも、水挿しの楽しいところですね。
植え付け前に確認!元気な苗に育てる管理のポイント
水挿しなどで無事に発根したら、すぐに畑に植え付けて良いわけではありません。
ここでひと手間かけることで、植え付け後の生長が大きく変わってきます。
まず確認したいのは、根の状態です。
白い根が数本出て、長さが5cm以上にしっかりと伸びているかを見ましょう。
根が短い状態で植えてしまうと、土の中でうまく水分を吸収できず、枯れてしまう原因になります。
また、新しい葉が青々と展開してきているかも、元気な苗かどうかの判断基準になります。
根が十分に伸びてきたら、いよいよ植え付けの準備です。
ただし、ずっと室内で育った苗を急に屋外の畑に植えると、環境の変化に驚いて弱ってしまうことがあります。
そのため、植え付けの数日前から、日中の暖かい時間帯だけ外に出して、少しずつ外の環境に慣らしてあげる「順化」という作業を行うと、植え付け後の失敗が格段に少なくなります。
今年の経験を来年に活かす!栽培と収穫のポイント

今年の栽培の振り返りと来年の計画の立て方
来年のさつまいも栽培をさらに成功させるためには、今年の経験を振り返ることがとても大切です。
「たくさん収穫できた」「思ったより大きくならなかった」など、結果だけではなく、その原因を考えてみましょう。
例えば、「日当たりがあまり良くない場所に植えてしまったかもしれない」「肥料をあげるタイミングが適切だったか」など、栽培中の記録や記憶を頼りに分析するのです。
うまくいった点は来年も継続し、失敗したと感じる点は改善策を考えます。
これを参考に、来年の計画を立てていきましょう。
植え付け場所を変えてみたり、畝の高さを工夫してみたり、違う品種の栽培に挑戦してみるのも良いかもしれません。
家庭菜園の楽しさは、このように試行錯誤を繰り返しながら、自分なりの育て方を見つけていくことにもあります。
今年の経験は、来年の豊かな収穫につながる貴重な財産となるはずです。
来年の収穫量を増やすための植え付けと管理方法
収穫量を増やすためには、植え付けの際のちょっとした工夫と、その後の管理がポイントになります。
さつまいもの苗を植える方法には、「船底植え」や「斜め植え」など、いくつかの種類があります。
一般的に、つるを長く土の中に埋める船底植えは、イモの数は多くなるものの小ぶりになりやすく、斜め植えは数は減るものの大きなイモが育ちやすいと言われています。
来年はどんなさつまいもを収穫したいかイメージして、植え方を選んでみるのも面白いでしょう。
そして、植え付け後に重要になるのが「つる返し」という作業です。
さつまいもは生長してくると、つるの途中にある節からも根(不定根)を地面に下ろしてしまいます。
これを放置しておくと、栄養が分散してしまい、本来大きくしたい株元のイモが育ちにくくなるのです。
そのため、定期的に伸びたつるを持ち上げて、途中から出ている根を剥がしてあげる作業が必要になります。
このひと手間が、秋の収穫量に大きく影響してきます。
収穫時期の見極め方と成功のポイント
丹精込めて育てたさつまいもは、最高のタイミングで収穫したいものですね。
収穫時期を見極めるには、いくつかの目安があります。
まず、植え付けからの日数を参考にします。
品種によって多少異なりますが、一般的には植え付けから120日から150日後くらいが収穫の適期とされています。
カレンダーに植え付けた日を記録しておくと良いでしょう。
また、見た目での判断も重要です。
秋が深まり、地上に出ている葉っぱが黄色く枯れ始めたら、土の中でイモが十分に大きくなったサインの一つです。
しかし、最も確実な方法は、試し掘りをしてみることです。
株元を少し掘ってみて、イモの太り具合を直接確認します。
十分な大きさになっていれば、いよいよ収穫です。
収穫する際は、イモを傷つけないように注意してください。
株元から少し離れた場所にスコップを入れ、土ごと大きく掘り上げるのが成功のポイントです。
晴れた日が数日続いた後、土が乾いている時に収穫作業を行うと、イモが傷みにくく保存性も高まります。
まとめ
今回は、収穫後に残るさつまいものつる(茎)を保存し、来年の栽培に活かす方法について詳しくご紹介しました。
これまで何気なく捨てていたつるが、来年の美味しいさつまいもに繋がると思うと、とてもワクワクしてきませんか。
つるを保存するメリットは、今年美味しかったさつまいもを来年も楽しめること、そして苗を購入するコストと手間を省けることです。
保存方法も、水に挿しておくか、プランターの土に挿しておくかという簡単な方法で、初心者の方でも十分に挑戦可能です。
大切なポイントは、冬の間、凍らせないように室内で管理することと、春になったら根を出させて元気な苗に育てることです。
今年の栽培での成功や失敗を振り返り、来年の計画に活かすことで、家庭菜園はもっと楽しく、奥深いものになります。
ぜひ、この記事を参考にして、さつまいものつるの保存と、来年の栽培に挑戦してみてください。
自分で繋いだ苗から育ったさつまいもを収穫する喜びは、きっと特別なものになるはずです。