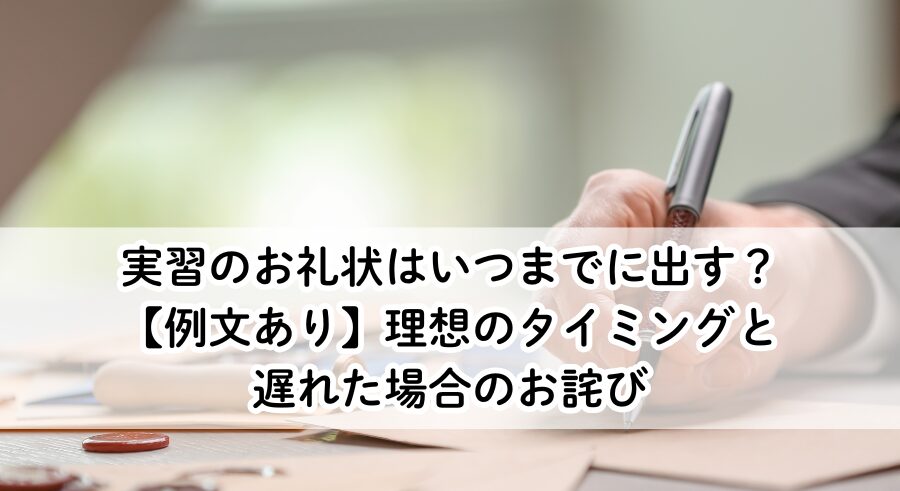実習のお礼状はいつまでに出す?【例文あり】理想のタイミングと遅れた場合のお詫び
無事に実習が終わり、ほっと一息ついている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実習はまだ完全に終わったわけではありません。
お世話になった実習先へ、感謝の気持ちを伝える「お礼状」を送るまでが実習です。
ただ、いざ書こうとすると、「お礼状って、そもそも必要なの?」「いつまでに出せばいいんだろう…」「もし出し忘れて遅くなってしまったら、どうしよう?」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるかもしれません。
お礼状一つで、あなたの印象が大きく変わることもあります。
この記事では、お礼状を出す理想のタイミングから、感謝が伝わる書き方の具体的なポイント、そして万が一遅れてしまった場合の誠実な対応方法まで、例文を交えながら詳しく解説していきます。
この記事を読めば、あなたの感謝の気持ちがしっかりと伝わり、実習先との良好な関係を築くための一助となるはずです。
最後まで読んで、自信を持ってお礼状を作成してください。
そもそも実習のお礼状は必要?出さないとどうなる?
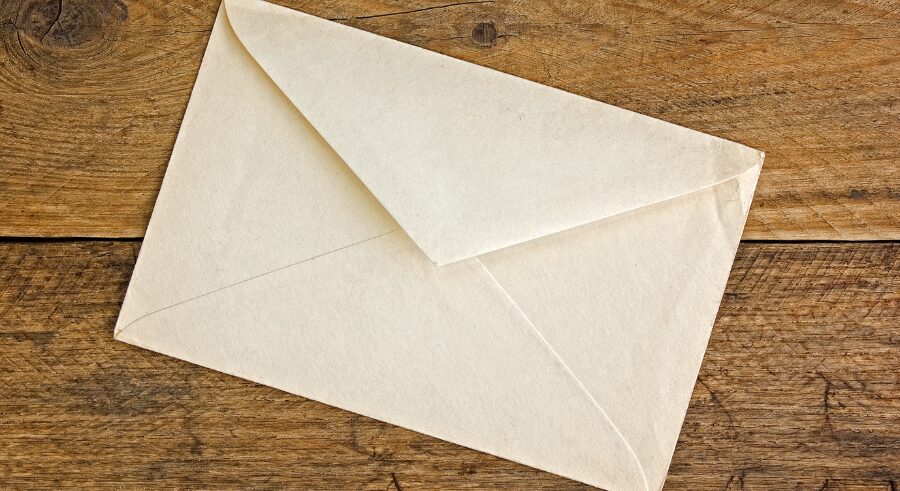
お礼状を出すことで得られる3つのメリット
実習後のお礼状は、単なる形式的なものではありません。
これには、今後のあなたにとってプラスに働く、大きく分けて3つのメリットが存在します。
まず一つ目は、感謝の気持ちを改めて伝え、社会人としての礼儀正しさを示せることです。
忙しい業務の合間を縫って指導してくださった方々へ、きちんと言葉で感謝を伝える姿勢は、非常に良い印象を与えます。
二つ目に、実習先との良好な関係を維持できる点が挙げられます。
その業界に進むのであれば、実習先の方と将来仕事で関わる可能性も十分に考えられます。
丁寧なお礼状を送ることで、あなたの誠実な人柄が伝わり、将来的なご縁につながるかもしれません。
そして三つ目は、実習での学びを自分の中で整理し、再確認できる機会になることです。
お礼状に何を書こうかと考える過程で、実習で得た経験や学びを振り返ることになり、それが自己成長へとつながるでしょう。
【要注意】もしお礼状を出さなかったら?考えられるデメリット
一方、もし実習のお礼状を出さなかった場合、いくつかのデメリットが考えられます。
最も大きなデメリットは、「礼儀を知らない」「感謝の気持ちがない」といったネガティブな印象を与えてしまう可能性があることです。
実習先の担当者は、時間と労力をかけてあなたを指導してくれました。
それに対して何の音沙汰もなければ、残念に思われてしまうのも無理はありません。
また、社会人としての常識を疑われてしまうかもしれません。
お世話になった相手にお礼を伝えるのは、基本的なビジネスマナーの一つです。
この基本ができていないと判断されると、あなたの評価に影響する可能性も否定できないのです。
さらに、あなた自身の学びの機会を逃すことにもなります。
前述の通り、お礼状を書く過程は実習を振り返る貴重な時間です。
これを行わないことで、せっかくの経験を深く自分の中に落とし込むチャンスを失ってしまうのは、非常にもったいないと言えるでしょう。
【例文でわかる】感謝が伝わるお礼状の書き方《完全ガイド》

まずは構成要素を理解しよう(お礼状の基本パーツ)
感謝の伝わるお礼状を書くためには、まず基本的な構成を知ることが大切です。
お礼状は、主に以下のパーツで成り立っています。
これらの流れを意識するだけで、格段に書きやすくなるはずです。
| 構成要素 | 内容 |
|---|---|
| 1. 頭語 | 手紙の冒頭に書く挨拶。「拝啓」が一般的です。 |
| 2. 時候の挨拶 | 季節に合わせた挨拶文。「〇〇の候、貴社におかれましては~」といった表現です。 |
| 3. 本文(お礼・エピソード) | 実習のお礼、学んだこと、印象に残っている具体的なエピソードなどを記述します。 |
| 4. 結びの挨拶 | 相手の発展を祈る言葉で締めくくります。「末筆ながら、貴社のますますのご発展を~」などが使われます。 |
| 5. 結語 | 手紙の最後に書く言葉。頭語が「拝啓」なら「敬具」で結びます。 |
| 6. 後付け | 日付、自分の氏名・大学名、宛名(会社名、部署名、担当者名)を記載します。 |
この基本構成に沿って、次のポイントを押さえることで、より気持ちの伝わるお礼状を作成できます。
ポイント① 具体的なエピソードで「自分だけのお礼状」にする
お礼状で最も大切なのは、あなたの感謝の気持ちを伝えることです。
そのためには、誰でも書けるような定型文を並べるだけでは不十分かもしれません。
あなたの言葉で、具体的なエピソードを盛り込むことが重要になります。
例えば、「〇〇の業務で失敗してしまった際に、△△様から『誰でも最初は同じだよ』と励ましていただき、最後までやり遂げることができました」といった個人的な体験を加えてみましょう。
指導担当者からかけてもらった印象的な言葉や、困難を乗り越えた経験などを具体的に書くことで、お礼状にオリジナリティが生まれます。
このように、あなただけが感じたことや学んだことを記述することで、感謝の気持ちがより深く、そして誠実に相手に伝わるのです。
実習中のメモや日誌を振り返り、心に残った出来事を思い出してみてください。
そのエピソードこそが、お礼状を特別なものにする鍵となります。
ポイント② 将来への意欲でポジティブな印象をプラス
感謝の気持ちや実習での学びを伝えることに加え、将来への意欲を示すことで、お礼状はさらにポジティブな印象を与えます。
実習を通じて得た経験を、今後どのように活かしていきたいのかを前向きな言葉で綴りましょう。
これは、単なるお礼に留まらず、あなたが実習から多くのことを学び、成長した証にもなります。
例えば、「〇〇様にご指導いただいたデータ分析の面白さに気づき、将来はマーケティングの分野で社会に貢献したいという思いが一層強くなりました」といった具体的な記述が効果的です。
このように、実習での経験が自分の将来の目標にどう結びついたかを明確にすることで、あなたの熱意や向上心を伝えることができます。
実習先の担当者も、指導した学生が前向きな目標を持つことは嬉しいものです。
あなたの将来性を感じさせる一文を添えることで、記憶に残るお礼状になるでしょう。
【NG例から学ぶ】これは避けたい…評価を下げてしまうお礼状
感謝を伝えるためのお礼状が、逆に評価を下げてしまうこともあります。
ここでは、避けるべきNG例をいくつか紹介します。
まず最も注意したいのが、誤字脱字や宛名の間違いです。
特に相手の名前や会社名を間違えるのは大変失礼にあたります。
これは、注意力が不足しているという印象を与えかねません。
次に、インターネット上の例文をそのまま丸写しにすることです。
具体的なエピソードがなく、誰にでも当てはまるような内容では、感謝の気持ちは伝わりにくいでしょう。
また、実習中の不満や愚痴といったネガティブな内容を書くのは絶対に避けるべきです。
たとえどんなに些細なことであっても、お礼状に書くべき内容ではありません。
最後に、あまりにも稚拙な言葉遣いや、友人へのメッセージのような砕けた文章も不適切です。
丁寧な言葉遣いを心がけ、社会人としてのマナーを示すことが大切になります。
これらの点に注意して、丁寧にお礼状を作成してください。
どうしても書くことが思いつかない時のヒント
「感謝の気持ちはあるけれど、具体的に何を書けばいいのか分からない」と悩んでしまうこともあるでしょう。
そのような時は、無理に文章をひねり出そうとせず、まずは情報を整理することから始めてみてください。
一番のおすすめは、実習中に書いた日誌やメモを読み返すことです。
そこには、日々の業務内容だけでなく、その時に感じたことや疑問に思ったこと、指導された内容などが記録されているはずです。
客観的な記録の中から、お礼状のヒントが見つかることは少なくありません。
もしメモなどがない場合は、以下の質問を自分に問いかけてみるのも良い方法です。
「実習全体で、一番印象に残っている出来事は何か?」「指導担当者のどの言葉が心に残ったか?」「実習前と後で、自分の中で最も成長したと感じる点はどこか?」などを自問自答してみましょう。
このように、少し視点を変えて実習期間を振り返ることで、書くべきエピソードが自然と思い浮かんでくることがあります。
【手紙・メール両対応】すぐに使える!基本のお礼状 例文
ここでは、手紙でもメールでも使える基本的なお礼状の例文を紹介します。
[ ] の部分を、ご自身の状況や具体的なエピソードに書き換えて活用してください。
—
件名:実習のお礼(〇〇大学 〇〇学部 氏名)
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇様
拝啓
〇〇の候、〇〇様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、先日は〇月〇日から〇日間にわたり、実習の機会をいただき、誠にありがとうございました。
実習期間中は、ご多忙にもかかわらず、〇〇様をはじめ皆様に大変丁寧なご指導を賜り、心より感謝申し上げます。
[ここに具体的なエピソードを記述]
(例:特に、〇〇の業務に携わらせていただいた際、私が作成した資料に対して〇〇様から具体的なアドバイスを頂戴し、仕事の進め方について多くを学ばせていただきました。)
今回の実習で得た貴重な経験を活かし、[今後の意欲を記述](例:将来は貴社のような〇〇業界で社会に貢献できる人材になりたいという思いが一層強くなりました)。
末筆ながら、貴社のますますのご発展と、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
敬具
[日付]
〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科
氏名
[連絡先:電話番号やメールアドレス]
—
【これで完璧!】お礼状を送る前の最終チェック&実践マナー

《手紙・はがきの場合》封筒の書き方と切手の注意点
手紙やはがきでお礼状を送る際は、中身だけでなく外見も大切です。
まず、封筒やはがきは白無地のシンプルなものを選びましょう。
キャラクターものや色付きのものは避けるのが無難です。
封筒の表面(宛名側)には、右から郵便番号、住所、会社名、部署名、役職、そして中央に一番大きく相手の名前を書きます。
会社名や部署名も略さず、正式名称で正確に記載することが重要です。
裏面には、左下に自分の住所、氏名、大学・学部名を記します。
封をしたら、中央に「〆」マークを書き入れましょう。
切手については、派手な記念切手は避け、通常の普通切手を使用するのが一般的です。
料金が不足しないよう、事前に郵便局やウェブサイトで確認しておくと安心です。
これらのマナーを守ることで、より丁寧な印象を与えることができます。
《メールの場合》送信前に確認すべき5つのポイント
メールでお礼状を送る場合にも、いくつか注意すべきマナーがあります。
送信ボタンを押す前に、以下の5つのポイントを必ず確認しましょう。
1. 分かりやすい件名にする
相手がひと目で内容を理解できるよう、「実習のお礼(〇〇大学 氏名)」のように、用件と差出人を明記します。
2. 宛名を正確に記載する
手紙と同様に、会社名、部署名、役職、氏名を正式名称で間違いなく入力します。
3. 機種依存文字は使用しない
丸付き数字や特殊な記号などは、相手の環境で文字化けする可能性があるため、使用を避けてください。
4. 本文に署名を入れる
メールの末尾には、自分の大学名、学部学科、氏名、連絡先(メールアドレス、電話番号)を記載した署名を忘れずに入れましょう。
5. 送信する時間帯に配慮する
深夜や早朝の送信は避け、実習先の就業時間内に送るのが基本的なマナーです。
これらのポイントを押さえることで、ビジネスメールとしての礼儀を示すことができます。
投函・送信前の最終チェックリスト
お礼状が完成したら、最後にもう一度見直すことが大切です。
うっかりミスを防ぐために、以下のチェックリストを活用してください。
投函・送信前の最終確認として、一つひとつ指差し確認するくらいの気持ちでチェックしましょう。
- □ 宛名(会社名・部署名・役職・氏名)は間違っていませんか?
- □ 誤字や脱字はありませんか?(声に出して読むと見つけやすいです)
- □ 自分の大学名や氏名は正しく書けていますか?
- □ 具体的なエピソードや学びは盛り込まれていますか?
- □ 前向きな意欲は伝えられていますか?
- □ 丁寧な言葉遣いになっていますか?
- □ (手紙の場合)切手の料金は不足していませんか?
- □ (メールの場合)件名や署名は入っていますか?
これらの項目をすべてクリアできれば、自信を持って送ることができます。
このひと手間が、あなたの誠実さを伝える上で非常に重要になります。
お礼状が遅れてしまった!ケース別のお詫びと誠実な対応法

まずは正直にお詫び!遅れても出すことが何より大切
「気づいたら実習終了から1週間も経ってしまった…」そんな時、焦りから出すのをためらってしまうかもしれません。
しかし、ここで最も良くない選択は、お礼状を出さないことです。
遅れてしまったとしても、お礼状は必ず出しましょう。
その際、何事もなかったかのように送るのではなく、まずは遅れてしまったことを正直にお詫びすることが何よりも大切です。
お詫びの言葉を一言添えるだけで、相手の印象は大きく変わります。
言い訳がましく長く書く必要はありません。
「本来であればすぐにでもお礼を申し上げるべきところ、ご連絡が遅くなり大変申し訳ございません」といったように、非を認めて謝罪する姿勢を示すことが、誠実な対応につながります。
遅れた事実から目を背けず、真摯に向き合うことが、信頼を損なわないための鍵となります。
【例文】体調不良や家庭の事情で遅れた場合のお詫び
体調不良や家庭の事情など、やむを得ない理由でお礼状が遅れてしまうこともあります。
そのような場合は、正直に、簡潔に理由を伝えるのが良いでしょう。
詳細に事情を説明する必要はなく、相手に心配をかけすぎない配慮も大切です。
以下に、お詫びの文章の例文を記載します。
お礼状の本文の前に、この一文を加えてください。
お詫びの例文(本文の前に加える)
「先日の実習では大変お世話になり、誠にありがとうございました。
本来であれば、実習後すぐにお礼を申し上げるべきところ、体調を崩しており、ご連絡が遅くなってしまいました。
大変申し訳ございません。
おかげさまで、現在は回復しております。」
このように、謝罪の言葉と、現在は問題ないという報告をセットにすると、相手も安心できます。
家庭の事情の場合も、「諸事情により」といった表現で差し支えありません。
【例文】就職活動や学業で遅れた場合のお詫び
実習後、すぐに就職活動の予定が詰まっていたり、学業が忙しくなったりすることもあるでしょう。
このような理由で遅れてしまった場合も、正直にお詫びの気持ちを伝えることが重要です。
ただし、忙しかったことを言い訳のように感じさせないための配慮が求められます。
あくまでも自分の段取りが悪かった、という姿勢で謝罪するのがポイントです。
以下に、お詫びの文章の例文を記載します。
この一文を、お礼状の本文の前に加えてみてください。
お詫びの例文(本文の前に加える)
「ご報告が遅くなりましたが、先日の実習では大変お世話になりました。
本来であれば、実習終了後すぐにお礼を申し上げるべきところ、就職活動(や学業)が立て込んでおり、ご連絡が遅くなってしまいました。
誠に申し訳ございません。」
このように簡潔に理由を述べ、謝罪することで、誠実な人柄が伝わるはずです。
【例文】1ヶ月以上など、大幅に遅れてしまった場合のお詫び
お礼状を出すのをすっかり忘れてしまい、1ヶ月以上など、大幅に時間が経過してしまったケースもあるかもしれません。
「今更出しても…」と諦めてしまう気持ちも分かりますが、それでも出さないよりはずっと良いです。
このような場合は、まず時間の経過に触れ、丁重にお詫びをすることが何よりも大切になります。
相手が自分のことを忘れている可能性も考慮し、いつ、どの実習でお世話になったかを明確に伝えましょう。
以下に、お詫びの文章の例文を記載します。
お詫びの例文(時候の挨拶の後に加える)
「大変ご無沙汰しております。
〇月〇日より〇日間、実習にてお世話になりました〇〇大学の〇〇です。
その節は、大変お世話になり、誠にありがとうございました。
本来であれば実習後すぐにお礼を申し上げるべきところ、大変遅くなり、誠に申し訳ございません。
今更のご連絡となり大変恐縮ですが、一言お礼を申し上げたく、筆をとりました。」
このように、深いお詫びの気持ちと、それでも感謝を伝えたいという真摯な姿勢を示すことが重要です。
まだある疑問を解決!実習お礼状のQ&A
- 手書きとパソコン(メール)、結局どちらがいいですか?
-
結論から言うと、基本的には手書きの方がより丁寧な印象を与え、感謝の気持ちが伝わりやすいとされています。
時間と手間をかけて書いたという事実が、誠実さの表れと受け取られるためです。
特に、医療や教育、公務員といった比較的伝統的な業界では、手書きのはがきや手紙が好まれる傾向にあります。
一方で、IT業界や外資系企業など、スピードや合理性が重視される業界では、メールでのお礼状でも問題ないとされることが多いです。
実習先の社風や担当者の雰囲気を考慮して判断するのが良いでしょう。
迷った場合は、より丁寧な手書きを選んでおけば間違いありません。 - 宛名は担当者個人宛?それとも部署宛?
-
宛名は、実習中、最もお世話になった指導担当者の方に個人宛で出すのが基本です。
その方の名前が分かる場合は、「〇〇部 部長 〇〇様」のように、役職と氏名を正確に記載します。
もし、指導担当者が複数名いた場合や、特定の方の名前が分からない場合は、「〇〇部 御中」や「人事部 実習ご担当者様」のように部署宛に送っても問題ありません。
ただし、その場合でも本文中には「〇〇様、△△様には特にお世話になりました」のように、名前が分かる方への言及を加えると、より気持ちが伝わります。 - お礼状に対して返信が来たら、さらに返信すべきですか?
-
メールでお礼状を送り、それに対して実習先から返信があった場合、基本的に再度の返信は不要です。
相手は忙しい業務の合間に返信してくれています。
こちらから返信を重ねることで、相手の時間をさらに奪ってしまう可能性があるためです。
相手の「返信不要です」という言葉がなくても、簡潔な労いやお礼のメールであれば、読んだことを確認するだけで大丈夫です。
ただし、相手からの返信に質問などが含まれている場合は、もちろん速やかに返信する必要があります。 - 複数人でお世話になりました。連名で出してもいいですか?
-
同じ実習先で複数人の学生がお世話になった場合でも、お礼状は一人ひとり個別に出すのが最も丁寧な形です。
連名で出すと、一人ひとりの感謝の気持ちや具体的な学びが伝わりにくくなってしまう可能性があります。
また、誰が主体となって書いたのかが分かりにくく、形式的な印象を与えてしまうかもしれません。
実習で感じたことや学んだことは、人それぞれ少しずつ違うはずです。
面倒に感じるかもしれませんが、あなた自身の言葉で、個別にお礼状を作成することをおすすめします。
その方が、より深く感謝の気持ちが伝わるでしょう。
まとめ
実習後のお礼状は、お世話になった方々へ感謝を伝える大切な機会であり、社会人としてのマナーを示す第一歩です。
この記事では、お礼状を出す理想のタイミングは「実習終了後3日以内」が望ましいことをお伝えしました。
感謝の気持ちを伝えるためには、定型文だけでなく、あなた自身の言葉で「具体的なエピソード」や「将来への意欲」を盛り込むことが非常に重要です。
また、手紙やメールの形式に応じたマナーを守り、投函・送信前には必ず最終チェックを行うようにしましょう。
万が一、お礼状を出すのが遅れてしまったとしても、決して諦めないでください。
遅れたことを正直にお詫びし、誠実な気持ちを伝えることが何よりも大切です。
お礼状の作成は少し手間がかかるかもしれませんが、あなたの丁寧な行動は、きっと実習先の方々の心に残ります。
この記事で紹介したポイントや例文を参考にして、あなたの感謝の気持ちがしっかりと伝わる、心のこもったお礼状を作成してください。