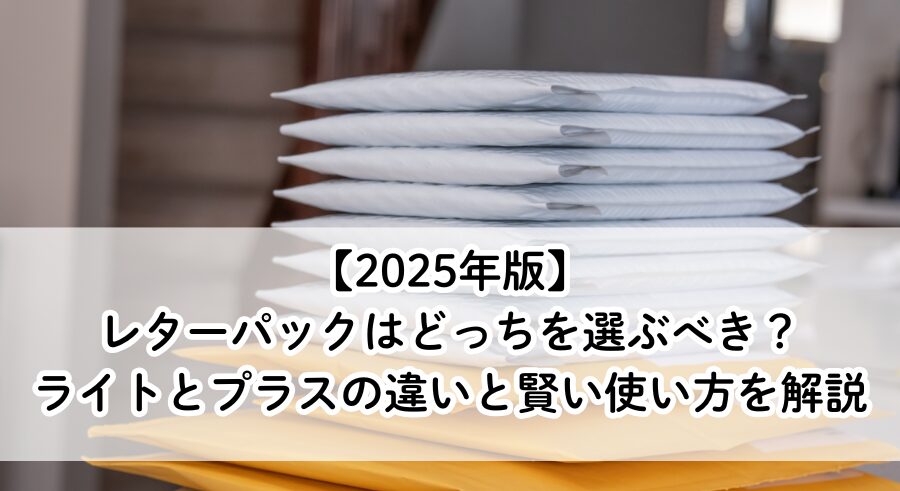【2025年版】レターパックはどっちを選ぶべき?ライトとプラスの違いと賢い使い方を解説
「この荷物、レターパックで送りたいけど、ライトとプラスのどっちがいいんだろう?」。
フリマアプリで商品を送るときや、大切な書類を送付する際に、このように迷った経験はありませんか?
レターパックは、全国一律料金で信書も送れる便利なサービスですが、ライトとプラスの2種類があり、それぞれの特徴を理解して使い分けることが大切です。
もし選び方を間違えてしまうと、荷物が返送されてしまったり、送料で損をしてしまったりすることもあるかもしれません。
この記事では、2025年最新の情報に基づき、レターパックのライトとプラスの違いを徹底的に比較し、どのような場合にどちらを選べば良いのかを分かりやすく解説していきます。
さらに、購入場所から正しい送り方、よくあるトラブルの対処法まで、レターパックを使いこなすための情報を網羅しました。
この記事を読めば、もうあなたはレターパック選びで迷うことはありません。
荷物に合わせて最適な選択ができるようになり、発送作業がもっとスムーズで快適になるはずです。
【どこで買う?】レターパックの販売場所

【基本中の基本】郵便局の窓口
レターパックを手に入れる最も確実な方法は、郵便局の窓口で購入することです。
全国各地にある郵便局の「郵便窓口」へ行けば、基本的に在庫切れの心配なく、1枚からでも必要な枚数を購入できます。
初めてレターパックを利用する方や、発送方法について少し不安がある方には特におすすめの方法と言えるでしょう。
なぜなら、購入する際に窓口の局員の方へ、送りたい荷物を見せて「これで送れますか?」といった質問ができるからです。
厚さや内容物についてその場で相談できるため、後からサイズオーバーで返送されてしまうといったトラブルを未然に防ぐことができます。
営業時間が限られているという点はありますが、その確実性と安心感は他の購入場所にはない大きなメリットです。
確実に、そして安心してレターパックを利用したいと考えるなら、まずは郵便局の窓口を訪れてみてください。
【一番手軽】コンビニでの取り扱い状況
レターパックは、私たちの生活に身近なコンビニエンスストアでも購入することが可能です。
郵便局の営業時間を気にすることなく、24時間いつでも購入できる手軽さが最大の魅力と言えます。
主に、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、そしてセイコーマートといったコンビニチェーンで取り扱いがあります。
ただし、注意点として、全ての店舗で必ず在庫があるわけではないことを理解しておく必要があります。
店舗によっては、ライトのみ、あるいはプラスのみしか置いていなかったり、人気のため品切れになっているケースも少なくありません。
また、店員さんがレターパックのサービスに詳しいとは限らないため、発送に関する相談は難しいでしょう。
とはいえ、急に発送が必要になった時や、日中忙しくて郵便局に行けない方にとっては、非常に頼りになる購入場所です。
近所のコンビニで手軽に購入できる便利さは、多くの方にとって大きなメリットになるはずです。
【まとめ買いに】ネット通販
仕事やフリマアプリなどで頻繁にレターパックを利用する方には、ネット通販でのまとめ買いが大変便利です。
一度に多くの枚数を購入しておくことで、いざ必要になった時に「手元にない!」と慌てる事態を防げます。
主な購入先としては、「日本郵便のネットショップ」が公式であり最も確実です。
ここでは20枚単位などでセット販売されており、自宅やオフィスまで届けてくれるため、買いに行く手間が省けます。
その他にも、Amazonや楽天市場などの大手通販サイトでも取り扱いが見られます。
これらのサイトでは、ポイントを利用して購入できたり、他の買い物と一緒に注文できたりするメリットがあります。
ただ、販売価格が定価と異なる場合があるため、購入前にはしっかりと価格を確認することが重要です。
計画的に発送作業を行う方や、少しでも手間を省きたい方にとって、ネット通販は非常に賢い選択肢となるでしょう。
【意外な穴場】金券ショップや一部のスーパー・書店
レターパックは、郵便局やコンビニ以外にも、意外な場所で購入できることがあります。
その一つが、金券ショップです。
金券ショップでは、レターパックが定価よりも少しだけ安く販売されていることがあります。
大量に利用する方にとっては、一枚数十円の差でも積み重なれば大きな節約につながるかもしれません。
ただし、在庫は常に変動するため、いつでも購入できるとは限らない点に注意が必要です。
また、一部のスーパーマーケットや書店などでも、切手やはがきを販売するカウンターでレターパックを取り扱っている場合があります。
これらの場所は、買い物ついでに立ち寄れる手軽さが魅力です。
「もしかしたら、あのお店にもあるかも?」と、普段利用するお店を一度チェックしてみるのも良いでしょう。
このような穴場スポットを知っておくと、急に必要になった際に役立つことがあるかもしれません。
【徹底比較】レターパックライトとプラス、あなたに合うのはどっち?

一目でわかる!ライトとプラスの違い 比較表
レターパックの「ライト」と「プラス」、この二つの違いが分からず迷ってしまう方は少なくありません。
どちらを選ぶべきか判断するためには、まずそれぞれの特徴を正確に把握することが大切です。
ここでは、料金から受け取り方に至るまで、両者の違いを分かりやすく表にまとめました。
この表を見れば、あなたの送りたい荷物にはどちらが適しているかが、きっと見えてくるはずです。
特に重要なポイントは、「厚さ」と「受け渡し方法」になります。
これらの違いが、どちらのサービスを選ぶかの大きな決め手となるでしょう。
| 項目 | レターパックライト | レターパックプラス |
|---|---|---|
| 料金(2025年現在) | 370円 | 520円 |
| サイズ | 34cm × 24.8cm(A4ファイルサイズ) | |
| 厚さ | 3cm以内 | 制限なし |
| 重量 | 4kg以内 | |
| 受け渡し方法 | 郵便受けへ配達 | 対面手渡し(受領印または署名) |
| 追跡サービス | あり | あり |
| 損害賠償(補償) | なし | なし |
| 集荷サービス | 不可 | 可能 |
【料金】150円の価格差をどう考える?(2025年現在の料金)
レターパックライトは370円、一方のレターパックプラスは520円と、両者の間には150円の価格差があります。
この150円という金額をどう捉えるかが、上手な使い分けの第一歩です。
結論から言えば、送る荷物が「厚さ3cm以内」に確実に収まり、かつ相手の郵便受けへのお届けで問題ない場合には、レターパックライトを選ぶのが最も経済的です。
例えば、フリマアプリで売れた薄手のTシャツや本、クリアファイルに入れた書類などを送る際には、ライトが最適でしょう。
しかし、もし荷物の厚さが3cmを超える可能性がある場合や、より確実に相手に届けたい重要な荷物である場合には、150円を「安心料」と考えることができます。
このため、厚手の衣類や、対面での受け渡しが望ましい契約書などを送る際には、迷わずプラスを選ぶべきです。
送料を少しでも抑えたい気持ちは分かりますが、荷物の内容や重要度に応じて、この150円の価値を判断することが重要になります。
【最大の壁】厚さ3cmの制限
レターパックライトを選ぶ際に、最も注意しなければならないのが「厚さ3cm以内」という制限です。
この「3cmの壁」が、ライトとプラスを分ける最大のポイントと言っても過言ではありません。
レターパックライトで送れるのは、例えば薄手のTシャツやブラウス、雑誌や書籍、クリアファイルに入れた数枚の書類など、明らかに厚みが出ないものです。
ポストに投函する際、少しでも引っかかるような感覚があれば、それは3cmを超えている可能性があります。
一方で、レターパックプラスにはこの厚さの制限がありません。
封筒が閉まりさえすれば、厚手のパーカーやジーンズ、箱に入った化粧品のセットや小型の雑貨なども送ることが可能です。
この「厚さ制限なし」という自由度の高さが、プラスの最大の強みです。
送りたい品物を梱包した状態で、厚さが3cmを超えるかどうかを冷静に判断することが、返送などのトラブルを避ける上で非常に重要になります。
【受け取り方】ポスト投函か、対面手渡しか
荷物の受け渡し方法の違いも、レターパック選びにおける重要な判断基準です。
レターパックライトは、受取人の郵便受けに直接投函されて配達完了となります。
これは、相手が日中不在がちな場合でも、時間を気にせず荷物を受け取れるという大きなメリットがあります。
ただし、郵便受けからの盗難のリスクや、雨で濡れてしまう可能性が全くないとは言い切れません。
これに対し、レターパックプラスは配達員が受取人に対面で荷物を手渡し、受領印またはサインをもらう仕組みです。
このため、送った側としては「確実に相手の手に渡った」という安心感を得ることができます。
大切な契約書や、高価ではないものの再発行が難しい書類などを送る際には、プラスを選ぶのが賢明でしょう。
もし受取人が不在の場合は、不在票が投函され、再配達を依頼することになります。
送料を抑え手軽さを取るならライト、安心と確実性を重視するならプラス、という視点で選ぶことが大切です。
【シーン別】もう迷わない!レターパックの賢い選び方

「レターパックライト」がおすすめなケース
では、具体的にどのような場合にレターパックライトを選べば良いのでしょうか。
結論として、ライトは「送料を抑えたい、かつ相手が不在でも届けたい薄いもの」を送るのに最適です。
例えば、フリマアプリで売れた薄手のTシャツやカットソー、ハンカチなどが典型的な例です。
これらは畳めば十分に3cm以内に収まるため、最も経済的な方法で発送できます。
また、雑誌やコミック、文庫本といった書籍類の発送にもライトは非常に便利です。
クリアファイルに入れた数枚の応募書類や、パンフレットなどを送る際にも重宝するでしょう。
いずれのケースにも共通するのは、荷物の厚みがなく、万が一郵便受けで何かあっても損害が比較的小さい、と考えられる点です。
相手の在宅時間を気にせず気軽に送りたい、そして少しでもコストを抑えたいというニーズに、レターパックライトはしっかりと応えてくれます。
「レターパックプラス」がおすすめなケース
一方、レターパックプラスが活躍する場面は、ライトでは対応できない状況です。
結論を言うと、プラスは「厚みが3cmを超えるもの、または確実に相手に手渡したい重要なもの」を送る場合に最適な選択肢となります。
具体例として、厚手のパーカーやセーター、ジーンズといった衣類が挙げられます。
これらは、どう畳んでも3cm以内にするのは難しいでしょう。
また、箱に入った化粧品のセットや、小型の電子機器のアクセサリー、厚みのある書籍などもプラスの出番です。
さらに、内容物が重要である場合もプラスが推奨されます。
例えば、署名・捺印が必要な大切な契約書や、再発行が困難な証明書の原本を送る際、対面手渡しで受領印がもらえるプラスの安心感は代えがたいものです。
返信用の封筒や書類を同封する場合も、厚みが増しがちなのでプラスを選んでおくと安心できます。
【重要】レターパックで送れないもの
レターパックは非常に便利なサービスですが、送ることができない品物が定められているため、注意が必要です。
最も重要なのは、現金や貴金属(指輪、ネックレスなど)、宝石といった貴重品は絶対に送ってはいけないということです。
その理由は、レターパックには万が一の紛失や破損に対する損害賠償、つまり「補償」が一切ないためです。
同様の理由から、スマートフォンやガラス製品、陶器といった壊れ物も送るべきではありません。
もし送る場合は完全に自己責任となり、配送中に壊れてしまっても誰も補償してくれません。
また、法律で定められた「信書」については、レターパックで送ることが可能です。
しかし、ゆうメールやゆうパックなどの他のサービスでは信書を送れないため、この点はレターパックの大きな利点と言えます。
ただし、請求書や契約書などが信書にあたるため、送る際はプラスを選ぶなど、その重要度に応じた判断が求められます。
これらのルールを守ることが、安全な利用の第一歩です。
【初心者でも安心】レターパックの送り方 3ステップ

Step1:宛名を書く
レターパックを購入したら、まず初めに行うのが宛名の記入です。
封筒の表面には「お届け先」と「ご依頼主」を記入する欄がはっきりと分かれているので、間違えないように注意深く書きましょう。
お届け先には、相手の郵便番号、住所、氏名、電話番号を正確に記入します。
ご依頼主の欄にも、あなた自身の情報を忘れずに記載してください。
もし配送中に何か問題があった場合、この依頼主情報をもとに荷物が戻ってきます。
そして意外と重要なのが「品名」欄です。
ここには、送るものの内容を具体的に書くことが推奨されています。
例えば、単に「雑貨」と書くのではなく「ハンカチ」「書籍」のように記載すると、配送がスムーズになることがあります。
特に航空機輸送が関係する場合、内容物が不明だと陸送に切り替えられ、配達が遅れる可能性があるからです。
もし壊れやすいものが含まれる場合は、品名欄の近くに「われもの注意」といったシールを貼っておくと、配達員の方への注意喚起になります。
Step2:荷物を入れて封をする
宛名の記入が終わったら、次は荷物をレターパックに入れて封をします。
品物を中に入れたら、封かんシールの剥離紙をゆっくりと剥がし、フタを閉じてしっかりと貼り付けましょう。
配送途中で封が開いてしまわないよう、隅々まで指で強く押さえて圧着することが大切です。
このとき、特にレターパックライトを利用する場合には、厚さが3cm以内に収まっているかを最終確認する必要があります。
簡単な確認方法としては、梱包後のレターパックを平らな机の上に置き、3cmの厚さの箱などを横に置いてみて、高さを比較する方法があります。
もし、専用の厚さ測定定規があれば、それを使ってスムーズにチェックできるでしょう。
少しでも膨らみが気になる場合は、中身の入れ方を工夫したり、テープなどで軽く押さえて厚みを均等にしたりする工夫も有効です。
ここで無理に詰め込むと、後で返送される原因になるため、慎重に確認してください。
Step3:発送する
荷物を封かんしたら、いよいよ発送です。
レターパックの発送方法は主に3つあり、あなたの都合の良い方法を選べます。
最も手軽なのは、街中にある郵便ポストへ投函する方法です。
これはレターパックライト、プラスのどちらでも可能で、厚みが許す限り、いつでも好きな時間に発送できます。
次に、郵便局の窓口へ直接持ち込む方法です。
この方法であれば、局員の方に厚さや重さを最終チェックしてもらえるため、最も確実で安心感があります。
特にプラスで厚みがギリギリの場合や、初めて発送する際には窓口への持ち込みがおすすめです。
そして、レターパックプラス限定の便利なサービスが「集荷サービス」です。
電話一本、またはウェブサイトから依頼すれば、配達員が自宅やオフィスまで荷物を受け取りに来てくれます。
荷物が多かったり、家を空けられなかったりする際に非常に助かるサービスなので、プラスを利用する際はぜひ活用を検討してみてください。
【失敗談から学ぶ】よくあるトラブルと解決策

最多トラブル!「厚さ3cmオーバー」で返送された時の対処法
レターパックライトで最も頻繁に起こる失敗が、厚さ3cmの制限を超えてしまい、自宅に返送されてくるケースです。
ポストに投函できたとしても、郵便局の仕分け作業の際に専用のスケールでチェックされ、オーバーしていると判断されると容赦なく戻ってきてしまいます。
もし荷物が返送されてしまった場合、落ち着いて対処しましょう。
主な対処法は二つあります。
一つ目は、郵便局の窓口へ返送されたレターパックライトを持ち込み、所定の手数料(差額の150円+交換手数料)を支払って、レターパックプラスに交換してもらう方法です。
これなら宛名を書き直す手間なく、すぐに再発送できます。
二つ目の方法は、ゆうパックや定形外郵便など、他の発送方法に切り替えることです。
荷物の内容や大きさによっては、レターパックプラスよりも安く送れる場合もあるため、一度料金を比較検討してみるのが良いでしょう。
いずれにしても、次回からは発送前に厚さをしっかり確認することが大切です。
宛名を書き損じた!手数料を払って新品に交換する方法
せっかくレターパックを用意したのに、宛名を書き間違えてしまった、という経験をしたことがある方もいるかもしれません。
インクが滲んでしまったり、住所を間違えたりすると、もう使えないと諦めてしまいがちです。
しかし、心配は不要です。
書き損じたレターパックは、郵便局の窓口で所定の手数料を支払うことで、新しいものと交換してもらえます。
この交換手数料は、2025年現在で1枚あたり42円となっています。
新品を買い直すよりもずっと安く済みますので、書き損じたからといって捨ててしまうのは非常にもったいないことです。
交換手続きは、お近くの郵便局の窓口に書き損じたレターパックを持参し、交換したい旨を伝えるだけです。
ただし、料額印面(切手部分)が汚れていたり、破れていたりすると交換できない場合があるため、その点は注意してください。
この制度を知っておけば、万が一書き間違えても、落ち着いて対処することができます。
紛失・破損したかも?補償はないけど、まずやるべき調査依頼
前述の通り、レターパックには紛失や破損に対する金銭的な補償がありません。
この点は、利用する上で必ず理解しておかなければならない重要なポイントです。
しかし、「追跡サービスで配達完了になっているのに、相手は受け取っていないと言っている」「何日も追跡情報が更新されない」といった事態が発生した場合、諦める前にやるべきことがあります。
それは、日本郵便への「調査依頼」です。
郵便局の窓口、または日本郵便のウェブサイトから、荷物の状況を詳しく調査してもらうよう依頼することができます。
この調査では、配達経路を遡って、どの段階で問題が発生したのかを調べてくれます。
調査の結果、誤って別の場所に配達されていたことが判明したり、見つからなかったりといった結果が報告されます。
残念ながら荷物が見つからないこともありますが、何もしないよりは発見の可能性が高まります。
補償がないからと泣き寝入りするのではなく、まずは公式な調査制度を利用して、状況の確認を依頼することが賢明な対応です。
雨対策は必須!中身を濡らさないための簡単梱包テクニック
レターパックの封筒自体は厚手の紙でできていますが、完全な防水仕様ではありません。
特に、郵便受けに配達されるレターパックライトの場合、雨の日に配達されると、郵便受けの形状によっては中身まで濡れてしまう可能性があります。
大切な書類や衣類が濡れてしまっては、せっかくの発送が台無しです。
そこで、一手間かけるだけで荷物を水濡れから守る、簡単な梱包テクニックを実践することをおすすめします。
最も簡単で効果的な方法は、荷物をレターパックに入れる前に、ビニール袋やOPP袋(透明でパリパリした袋)に入れることです。
衣類や書籍なら大きめのビニール袋に、書類ならクリアファイルに入れた上でさらにOPP袋に入れると、より安心できます。
この一手間をかけるだけで、万が一レターパックの外側が濡れてしまっても、中身への被害を最小限に食い止めることが可能です。
これは送る側としてのマナーでもあり、受け取る相手への配慮にもつながります。
特に梅雨の時期や天候が不安定な季節には、忘れずに行いたい対策です。
【作業効率UP】レターパック発送に役立つ便利グッズ3選

① 厚さ測定定規
レターパックライトを頻繁に利用する方にとって、「3cmの壁」は常に付きまとう課題です。
目分量で確認するのは不安が残り、その都度定規を当てるのも少し面倒に感じるかもしれません。
そこで非常に役立つのが、「厚さ測定定規(スケール)」です。
この定規には、定形郵便やレターパックライトなどの規格に合わせた厚さの測定用の穴が開いています。
梱包した荷物をこの定規の「3cm」の穴に通すだけで、厚さ制限をクリアしているかどうかを瞬時に、そして正確に判断できます。
もう「大丈夫かな?」と心配する必要はありません。
この厚さ測定定規は、事務用品店やインターネット通販などで購入できるほか、最近では100円ショップでも見かけることがあります。
一つ持っておくだけで、発送前の不安が解消され、作業効率が格段にアップするでしょう。
フリマアプリのヘビーユーザーや、小規模なネットショップを運営している方には、特におすすめしたい便利グッズです。
② 宛名ラベルシール
一度にたくさんのレターパックを送る場合や、手書きの文字に自信がないという方におすすめなのが「宛名ラベルシール」です。
毎回手書きで宛名を記入するのは、時間がかかるだけでなく、書き損じのリスクも伴います。
宛名ラベルシールを使えば、パソコンで作成した住所録データなどから、簡単かつ綺麗に宛名ラベルを印刷できます。
これにより、見た目が美しくなるだけでなく、読み間違いによる誤配のリスクを減らすことにも繋がります。
特に、同じ相手に何度も送る場合や、フリマアプリの取引で得た送付先情報を管理している場合には、データを活用して印刷するだけなので作業が大幅に楽になります。
ご依頼主(自分)の住所氏名をあらかじめ印刷したシールを用意しておくだけでも、毎回書く手間が省けて非常に効率的です。
各種文具メーカーから様々なサイズやタイプのラベルシールが販売されていますので、自分の使いやすいものを選んで活用してみてください。
③ 緩衝材(プチプチ)と防水用OPP袋
レターパックには補償がないため、中に入れる荷物をしっかりと保護するのは、発送する人の大切な役割です。
そこで最低限用意しておきたいのが、緩衝材と防水用の袋です。
緩衝材、いわゆる「プチプチ」は、衝撃から荷物を守るための必需品です。
少しでも壊れる可能性がある小物や、角が折れやすい書籍などを送る際には、必ず緩衝材で一巻きしてから封筒に入れましょう。
この一手間が、配送中の万が一の衝撃から大切な荷物を守ってくれます。
また、前述の通り、雨などによる水濡れ対策も欠かせません。
そのために役立つのがOPP袋です。
商品をOPP袋に入れてから緩衝材で包む、という順番で梱包すれば、防水と耐衝撃の両方の対策ができます。
これらの梱包材は、100円ショップやホームセンター、文房具店などで手軽に入手可能です。
丁寧な梱包は、トラブルを防ぐだけでなく、受け取った相手に良い印象を与えることにも繋がる大切なマナーです。
【もっと便利に】レターパック活用術&豆知識Q&A
【フリマユーザー必見】送料で損しない梱包と発送のコツ
フリマアプリの利用者にとって、送料は利益に直結する重要な要素です。
レターパックは便利な選択肢ですが、他のサービスと比較して本当に最適かを見極めることが、損をしないためのコツになります。
例えば、メルカリの「ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットポスト)」や、PayPayフリマの「おてがる配送(ゆうパケットポスト)」といった匿名配送サービスは、薄いものであればレターパックライトより安価に送れる場合があります。
匿名で送受信できるという大きなメリットもあるため、個人情報を相手に伝えたくない場合には、これらのサービスが有力な候補となるでしょう。
商品を「送料込み」で出品する際は、あらかじめどの配送方法を使うかを想定し、その送料を上乗せして価格設定することが基本です。
衣類であれば、畳み方を工夫して厚さを3cm以内に抑えられればライト、難しければプラス、というように、梱包後のサイズをイメージして、最適な送料を計算に入れることが賢明な判断と言えます。
定形外郵便やゆうパックとの使い分けは?
レターパック以外にも、郵便局には様々な発送サービスがあります。
「定形外郵便」や「ゆうパック」と、レターパックをどのように使い分ければ良いのでしょうか。
判断のポイントは「重さ」「追跡の要否」「補償の要否」です。
まず、非常に軽くて小さいもの(例:50g以内のアクセサリーなど)で、追跡が不要な場合は、定形外郵便が最も安くなる可能性があります。
逆に、レターパックの専用封筒に入らない大きなものや、高価で補償が必要なものを送りたい場合は、「ゆうパック」一択です。
ゆうパックには、サイズに応じた料金設定、しっかりとした損害賠償制度、そして配達日時指定のサービスがあります。
以下に簡単な判断フローを示します。
- A4サイズ・厚さ3cm・重さ4kg以内か? → YESならレターパックライトを検討
- A4サイズ・重さ4kg以内で厚さ3cm超えるか? → YESならレターパックプラスを検討
- 軽くて小さく、追跡も補償も不要か? → YESなら定形外郵便を検討
- 大きくて重い、または高価で補償が必要か? → YESならゆうパックを選択
このように、送りたい荷物の特徴に合わせてサービスを選ぶことが、最も合理的で無駄のない発送に繋がります。
よくある質問(Q&A)
ここでは、レターパックに関して多くの人が疑問に思う点をQ&A形式で解説します。
- 配達日数は?土日祝も配達される?
-
はい、レターパックは土曜日、日曜日、祝日にも配達されます。配達日数は、おおむね速達に準じており、多くの地域で翌日か翌々日には届きます。正確な日数は日本郵便のウェブサイトで確認できます。
- 古い料額のレターパックは使える?
-
はい、使えます。料金が改定される前の古いレターパック(例: 510円のプラス、360円のライト)を持っている場合、差額分の切手を貼ることで、現在も問題なく使用できます。
- 配達日や時間帯の指定はできる?
-
いいえ、レターパックは配達日や時間帯の指定はできません。もし日時指定が必要な場合は、ゆうパックを利用する必要があります。
- 海外へは送れる?
-
いいえ、レターパックは日本国内専用のサービスです。海外へ荷物を送ることはできません。海外発送の場合は、国際郵便などのサービスを利用してください。
- 折り曲げてポストに入れても平気?
-
中身に影響がない限り、レターパック本体を二つに折り曲げてポストに投函すること自体は問題ありません。ただし、中の書類が折れては困る場合や、厚みが増して投函口に入らなくなる場合は避けるべきです。
まとめ:レターパックを賢く使って、発送をもっと快適に
今回は、レターパックのライトとプラスの違いを中心に、その賢い使い方を詳しく解説してきました。
改めてポイントを整理すると、「薄くて送料を抑えたい荷物にはライト」、「厚みがある、または確実に手渡ししたい重要な荷物にはプラス」を選ぶのが基本です。
この二つの特徴を理解し、送る品物や状況に応じて的確に使い分けることが、送料の節約やトラブルの回避に繋がります。
また、購入場所が郵便局だけでなくコンビニやネット通販にも広がっていることや、宛名の書き方、梱包の小さな工夫が、発送作業をよりスムーズにしてくれることもお分かりいただけたかと思います。
もし書き損じたり、厚さオーバーで返送されたりといった失敗をしても、適切な対処法を知っていれば慌てる必要はありません。
この記事で得た知識を活用すれば、あなたはもうレターパックの前で迷うことなく、自信を持って最適な選択ができるはずです。
日々の発送作業を、もっと賢く、もっと快適なものにしていきましょう。