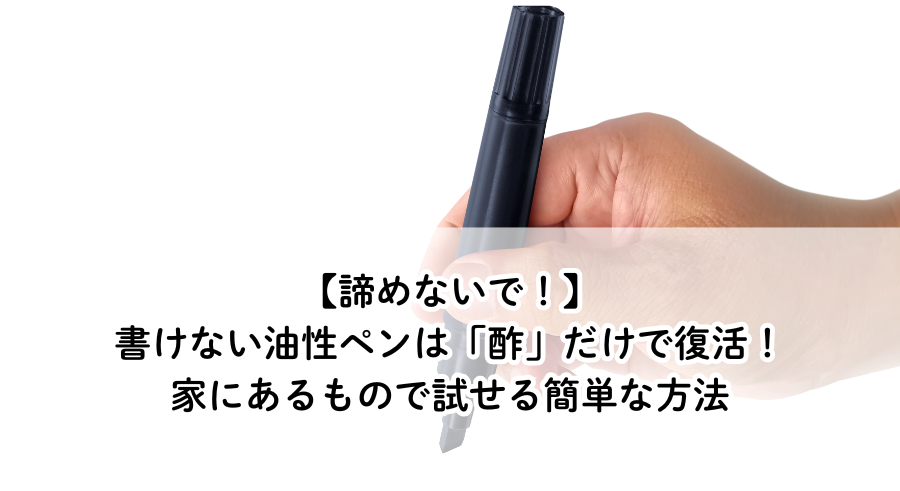「いざ、サインをしよう!」「名前を書かなくちゃ!」という大事な場面で、油性ペンがかすれて書けなくなってしまった経験はありませんか。
多くの場合、「もう寿命かな」と諦めて捨ててしまうかもしれません。
しかし、実はその油性ペン、家にある「あるもの」を使えば簡単に復活させられる可能性があるのです。
そのあるものとは、なんと「お酢」。
この記事では、お酢を使って書けなくなった油性ペンを復活させる驚きの方法を詳しく解説します。
他にも、お酢がない場合に使える除光液やアルコールを使った方法もご紹介。
油性ペンが書けなくなる原因から、復活方法を試す際の注意点、さらにはペンを長持ちさせるコツまで、気になる情報をまとめました。
インクが残っているのに書けないからと、すぐに諦めてしまうのはもったいないかもしれません。
この記事を読んで、ぜひご家庭で眠っている油性ペンの復活を試してみてください。
油性ペンが書けなくなる主な原因とは?

原因1:ペン先のインクの乾燥
油性ペンが書けなくなってしまう最も多い原因は、ペン先のインクが乾燥してしまうことです。
油性ペンのインクには、色を付ける顔料のほかに、それを溶かすための有機溶剤が含まれています。
この溶剤は揮発性が高い、つまり蒸発しやすい性質を持っているのが特徴です。
そのため、ペン先が空気に触れていると、インクの中の溶剤だけがどんどん蒸発してしまいます。
結果として、ペン先に残った顔料などの成分が固まってしまい、インクの通り道を塞いでしまうのです。
これが、かすれや書けなくなる状態を引き起こす主なメカニズムです。
インク自体はまだペンの中にたくさん残っているのに、出口が詰まってしまって出られない状態と言えるでしょう。
この乾燥したインクを再び溶かすことが、油性ペンを復活させるための鍵となります。
原因2:長期間使っていなかった(使用頻度の低さ)
キャップをしっかり閉めて保管していたとしても、油性ペンを長期間使わずに放置してしまうと書けなくなる原因になります。
これは、ペンの内部でインクの流動性が失われてしまうためです。
長期間動かさないでいると、インクの中の成分が分離したり、溶剤がわずかずつ揮発してインク全体の粘度が高くなったりすることがあります。
インクがドロッと硬い状態になってしまうと、ペン先までスムーズに流れなくなり、結果としてかすれたり書けなくなったりしてしまうのです。
特に、一度使ったペンは、新品の状態よりもインクが空気に触れているため、この現象が起きやすくなります。
たまにしか使わない油性ペンほど、いざ使おうと思った時に書けないという事態に陥りやすいのは、このような理由からです。
定期的に少しでもペンを動かしてインクを流動させることが、実は長持ちの秘訣の一つとも言えます。
原因3:キャップの閉め忘れや保管方法の問題
ペン先のインクの乾燥を引き起こす最も直接的で多い原因が、キャップの閉め忘れです。
「後でまたすぐ使うから」と、ついキャップを閉めずに置いてしまうと、ペン先は無防備に空気にさらされ続けます。
前述の通り、油性インクに含まれる溶剤は非常に揮発しやすいため、わずかな時間でも乾燥が進んでしまうのです。
油性ペンを使い終わったら、「カチッ」と音がするまでしっかりキャップを閉める習慣をつけることが何よりも重要です。
また、保管する場所もペンを長持ちさせる上で気をつけたいポイントになります。
例えば、直射日光が当たる場所や、夏場の車内のような高温になる場所に放置すると、ペンの内部でインクの劣化や乾燥が早まる可能性が高まります。
正しい保管方法を心がけるだけで、油性ペンが使えなくなるリスクを大きく減らすことができるでしょう。
【家にあるもので簡単】油性ペンを復活させる方法3選

【一番おすすめ】お酢を使った一番簡単な復活方法
書けなくなった油性ペンを復活させる方法として、最も手軽でおすすめなのが「お酢」を使うやり方です。
なぜなら、お酢に含まれている「酢酸」という成分が、固まってしまった油性インクの溶剤を溶かす働きをしてくれるからです。
ご家庭にある穀物酢や米酢などで試すことができます。
方法は非常に簡単です。
まず、ペットボトルのキャップや小さな豆皿のような、ペン先だけを浸せるくらいの小さな容器を用意してください。
そこに少量のお酢を入れ、書けなくなった油性ペンのペン先をそっと浸します。
時間は数分程度で十分です。
その後、ペン先をティッシュなどで軽く拭き取り、いらない紙の上で試し書きをしてみてください。
最初はかすれていた線が、だんだんとはっきりと書けるようになる場合があります。
家にあるものですぐに試せる、一番簡単な復活方法です。
【酢がない時に】除光液を使った復活術
もしご家庭にお酢がない場合や、お酢で試しても効果がなかった場合に使えるのが「除光液」です。
マニキュアを落とすために使われる除光液には、「アセトン」などの有機溶剤が含まれています。
この成分は、お酢よりも強力に油性インクを溶かす効果が期待できるのです。
やり方はお酢の場合とほとんど同じです。
小さな容器に少量の除光液を入れ、そこにペン先を浸します。
ただし、除光液は成分が強力なため、ペン先を浸す時間は1分程度と、お酢の時よりも短めにすることをおすすめします。
長く浸しすぎると、ペン先のプラスチック部分を傷めてしまう可能性があるため注意が必要です。
浸した後は、ティッシュでインクと除光液をよく拭き取り、試し書きをして復活したか確認してください。
強い匂いがするため、この方法を試す際は必ず換気を行うようにしましょう。
【こちらも使える】無水エタノールなどアルコールの活用法
お酢や除光液の他にも、アルコール類を使って油性ペンを復活させることができる場合があります。
特に効果が期待できるのは、理科の実験などでも使われる「無水エタノール」です。
無水エタノールはアルコール濃度が非常に高いため、油性インクの溶剤として働き、固まったインクを溶かしやすくしてくれます。
もしご家庭に無水エタノールがなくても、手指の消毒用に使われる消毒用アルコールで代用できる可能性もあります。
ただし、消毒用アルコールは製品によってアルコール濃度が異なるため、無水エタノールに比べると効果は少し落ちるかもしれません。
使い方はこれまで紹介した方法と同じで、容器に入れたアルコールにペン先を短時間浸し、拭き取ってから試し書きをします。
アルコール類も揮発性が高く特有の匂いがあるため、使う際には換気をしっかり行うことが大切です。
試す前に確認!復活方法を試す時の注意点

使う材料の確認と換気の必要性
油性ペンの復活方法を試す前には、いくつか注意すべき点があります。
まず、今回紹介したお酢や除光液、アルコールといった材料は、それぞれ特有の匂いを持っています。
特に、除光液や無水エタノールは揮発性が高く、強い匂いを放ちます。
狭い部屋で作業をしていると、気分が悪くなってしまう可能性も考えられます。
そのため、これらの復活方法を試す際は、必ず窓を開けるなどして、部屋の換気をしっかり行うようにしてください。
また、肌が弱い方は、念のためビニール手袋などを着用して、液体が直接肌に触れないようにするとより安心です。
小さなお子さんやペットがいるご家庭では、誤って口にしてしまわないよう、材料の管理にも十分気をつける必要があります。
安全に作業を行うための、大切なポイントです。
ペン先を傷めないためのポイント
油性ペンのペン先は、インクをスムーズに送り出すための非常にデリケートな部分です。
復活を試みる際には、このペン先を傷めないように注意することが重要になります。
お酢や除光液などの液体にペン先を浸す時間は、必要以上に長くしないようにしましょう。
長時間浸しすぎると、ペン先の繊維やプラスチック部分が劣化してしまったり、インクが溶け出しすぎてしまったりする原因になります。
まずは1分から数分程度を目安にして、様子を見ながら行うのがおすすめです。
また、インクが出るか試す際に、焦ってペン先を紙に強く押し付けたり、コンコンと叩きつけたりするのは避けてください。
ペン先が潰れてしまい、かえってインクが出なくなる可能性があります。
あくまで「優しく」「軽く」扱うことを心がけるのが、復活を成功させるためのポイントです。
復活したかどうかの結果を確認する方法
液体に浸してペン先をきれいさっぱりさせた後、本当に復活したかどうかを確認する手順も大切です。
まず、ペン先をお酢や除光液から取り出したら、ティッシュペーパーや布で優しく拭き取ります。
この時、ペン先に残った余分な液体と、溶け出した古いインクをしっかり吸い取ることがポイントです。
次に、広告の裏など、汚れてもいい不要な紙を用意して、試し書きをしてみましょう。
すぐにインクが出なくても諦めないでください。
最初はかすれているかもしれませんが、ぐるぐると円を描いたり、線を引いたりしているうちに、ペン内部の新しいインクがペン先まで届き、スムーズに書けるようになることが多いです。
もし一度の挑戦で結果が出なくても、インクがまだ残っているようであれば、もう一度同じ方法を試してみる価値はあります。
根気よく試すことが成功への近道です。
【気になる】復活させた油性ペンのその後と長持ちのコツ

復活後のインクはどれくらい持つ?
お酢などを使って見事に復活した油性ペンですが、その効果がどれくらい持続するのかは気になるところだと思います。
結論から言うと、これはペンの状態やインクの残量によって大きく変わるため、一概には言えません。
多くの場合、この復活方法はあくまで「応急処置」と考えるのが良いでしょう。
ペン先の詰まりが解消されただけで、中のインク自体が新品に戻るわけではないからです。
そのため、一度は書けるようになっても、またすぐにインクがかすれてきてしまう可能性はあります。
特に、もともとのインク残量が少なかった場合は、すぐに使い切ってしまうことも考えられます。
ただ、「今、この瞬間に少しだけ使いたい」という場面では非常に役立つ方法です。
復活させたペンがいつまで使えるかは一概に言えませんが、捨てる前に一度試す価値は十分にあると言えるでしょう。
油性ペンを長持ちさせる正しい保管方法のすすめ
油性ペンを一度復活させても、またすぐに書けなくなっては意味がありません。
そもそも、ペンをできるだけ長く使えるようにするためには、日頃の保管方法が非常に重要になります。
油性ペンを長持ちさせる一番のコツは、インクの乾燥を防ぐことです。
そのためには、まず「使ったらすぐにキャップをしっかり閉める」という基本を徹底しましょう。
「カチッ」という音がするまで確実に閉めることで、ペン先の気密性が保たれます。
また、ペンの保管向きもポイントです。
ペン立てなどでペン先を上に向けて保管すると、重力でインクが下に下がってしまい、ペン先が乾燥しやすくなります。
できるだけ横向きに置くか、ペン先を少し下向きにして保管するのがおすすめです。
そして、前述の通り、直射日光が当たる場所や高温になる場所は避けて保管することも大切です。
これらの簡単な習慣を気をつけるだけで、お気に入りの油性ペンを長く使い続けることができます。
まとめ
今回は、書けなくなってしまった油性ペンを家にあるもので簡単に復活させる方法について、詳しくご紹介しました。
この記事のポイントを最後におさらいしましょう。
まず、油性ペンが書けなくなる主な原因は、ペン先に残ったインクが乾燥して固まってしまうことです。
この固まったインクを溶かすために効果的なのが、家にある「お酢」です。
お酢に含まれる成分がインクを溶かし、再び書けるようにしてくれる可能性があります。
方法は、少量の酢にペン先を数分浸すだけと、非常に簡単です。
もしお酢がない場合は、除光液や無水エタノールなども代用として使えます。
ただし、これらの方法を試す際は、必ず換気をしっかり行い、ペン先を長時間浸しすぎないように注意が必要です。
また、ペンを長持ちさせるためには、使い終わったらすぐにキャップを閉め、横向きに保管するといった日頃の使い方も大切になります。
インクが残っているのに書けなくなった油性ペンを、すぐに捨ててしまう前に、ぜひ一度この復活方法を試してみてはいかがでしょうか。